
書誌
以下は、自分に影響を与えたテキスト群です。 もちろんこれですべてというわけではありませんが、まずはテキストをある程度の数ここにとりまとめ(数百件程度)、その上で、複数書籍を横断する索引を作るイメージで、データベース化に着手します。 デザイン全般、グラフィックデザイン、タイポグラフィ、タイプフェイス、文学、哲学、芸術にわたる内容になると思われます。 (メモ) タイポグラフィ関連書籍をまとめなければ……。 佐藤敬之輔関連書籍、森啓、小宮山博史、府川充男らによる書籍。朗文堂によるいくつかの書籍。いくつかの単行本や見本帳などに関する書籍、たとえば小池光三『印刷デザイン』、小泉均『タイポグラフィ・ハンドブック』など。構成関連の本もここにいれるべきか? グラフィックデザイン誌、タイポグラフィックス・ティー誌、アイデア誌、デザイン誌などの雑誌記事もあるだろうし、業界史に関する書籍もあるだろう。小林章氏による本もあるだろう。近年の傾向として小塚昌彦、鳥海修、藤田重信ら書体デザイナーによる書体デザインを語った書籍類もあるだろう。文学や書誌学の方面からも論じることができるだろう。実学的な方面から論じること、歴史的な方面から論じること、人文学的、芸術学的な方面から論じること、技術史的な方面から論じること……その広範さにくじけそうになるが、これはタイポグラフィに特有なことにも思えるがデザインに特有なことでもあるといえるか。* * *
近代の美術史のもう一人の創設者、エルヴィン・パノフスキーは、有名な論文「象徴形式としての遠近法」(1924–25)で、ギリシャ人たちの「集積的」な空間とイタリア・ルネサンスの「体系的」な空間を対象させた。パノフスキーは、空間表象の歴史と抽象的思考の発展の間に併行関係を打ち立てた。前者は、古代における個々の対象から成る空間から、近代における連続的で体系的な空間の表象へと移行する。それに応じて、抽象的思考の発展も、物理的世界を非連続的で「集積的」とみなす古代哲学の見方から、空間を無限で、均質で、等方性を持ち、対象に先んじて存在するもの──要するに、体系的なもの──とするポスト・ルネサンスの理解と移っていくのである。 ──レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語:デジタル時代のアート、デザイン、映画』堀潤之〔訳〕ちくま学芸文庫、筑摩書房、2023年7月10日、p. 528。Lev Manovich, The Language of New Media, Massachusetts: MIT Press, 2001.
レフ・マノヴィッチ Lev Manovich(b. 1960) 堀潤之 Junji Hori エルヴィン・パノフスキー Erwin Panofsky(1892–1968)
彼はひそかに出かけました。桜の森は満開でした。一足ふみこむとき、彼は女の苦笑を思いだしました。それは今までに覚えのない鋭さで頭を斬りました。それだけでもう彼は混乱していました。花の下の冷めたさは涯のない四方からドッと押し寄せてきました。彼の身体は忽たちまちその風に吹きさらされて透明になり、四方の風はゴウゴウと吹き通り、すでに風だけがはりつめているのでした。彼の声のみが叫びました。彼は走りました。何という虚空でしょう。彼は泣き、祈り、もがき、ただ逃げ去ろうとしていました。そして、花の下をぬけだしたことが分ったとき、夢の中から我にかえった同じ気持を見出しました。夢と違っていることは、本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでありました。 ──坂口安吾『桜の森の満開の下』1947年。
坂口安吾 Ango Sakaguchi
文字のおちつきと共に大切なことは、親しみがあるということである。理論的にどんなに完全に安定のとれた字体であっても、あまり一般概念から遠い、見慣れない形であっては、決して読みよいものではない。文字は伝統的に、一般に受入れられている姿かたちから、かけ離れないことが、読みやすさの重要な要素となる。 ──今井直一(タイポグラファー/『書物と活字』1949より)
今井直一 Naoichi Imai
本文用の書体に関する限り、いわゆる個人的な好みだけではすまされないという問題がある。つまり、個人的な次元から、広く一般にも共有される社会的なものへ止揚されなければ、本文用として普遍性をもち、広く社会に受け入れられることはないといえる。文字印刷は、その内容をより多くの人たちに読まれ、それが社会化されることを前提にしているからである。 ──矢作勝美(印刷史研究者/『明朝活字』1976より)
矢作勝美 Katsumi Yahagi (b. 1928)
一般の読者の方は、書と活字を全く切り離している。活字の姿には類型化が必要であって、人々は『馴れ』によってそれを読み取っている。しかしぎりぎりのところへ行くと、やはりそこに、人間性の温かみがこもっていないと、文字としての魅力が失われ、無意識のうちに、人々を引きつけている愛着のきずなが断ちきられる。 ──佐藤敬之輔(書体デザイナー/『佐藤敬之輔記念誌』 1982より)
佐藤敬之輔 Keinosuke Sato (1912–1969)
● 高校時代をふりかえって 当時の高校生はエリートでした。日本の文化をリードしなくてはいけないという責任感がありました。そういうものがあるからこそエリートと言われるわけです。自分の利益のみに動くのではない。(略)ある文化とそれを取りまくその他の分野の関係は大切で、全体で把握しているかどうかが問題です。一分野の速成の専門家は、悪い意味で専門分野以外のことは何も知らないと言えるのではないでしょうか。(略)クリエイティブな専門家になるためには、ゼネラリストにならなければいけない。ピラミッドの底辺があって、スペシャリストの高さがある。スペシャリストとして地位を高めるためには、底辺をますます広げていかなければならないわけです。 ● 1932年20歳の時(高校時代の教師の評価) 武蔵高校学籍簿に担任の玉虫文一は次のような所見を記している。「感受性強く情操に富む。外見女性的内心自身力強く、強情、ワガママ、温順優雅。若者の感なく老成を思わしむ。/努力せず天才的。本をよく読み博識群を抜いている。/文才あり。絵画に天分あり。これが為に身を誤ることにならなければ良いが。/多趣味、多才の士なり。身体剛健ならず」。 ● 1947年33歳の時(鹿児島/横浜) 私はゆうべも三時ごろまでここの二回で自分の旧作〔詩〕をみていました。それは前途遼遠な道ではあるが、自分が最も真実に生きる一本の道ではありましょう。(略)芸術家でなくってもいっこうにかまわないが、しかし一生のうちに本当の作品を作りたい。自分を打ち出すという事に長い間苦しんで来たのです。 ● 1948年34歳(鹿児島/横浜) 琴線が強くはられ、詩のしらべが出ようとしています。おそい成長でした。いつでも調子をおとしてしまうような心を、僕は最大の努力をもってふるいおとしていましたが、こんどはやや思うようになりましょう。燃えるでしょう。発表しようとすると、しかし自分の力をみつめるおそろしさでたじろぎます。まあいい。四十までは忍耐です。少しづつ、少しづつ沈積するのを待つ他ありません。 ● 1950年38歳(GHQ印刷所に入所) 有楽町にあったCIE図書館でゴーディの80歳の記念出版物である赤表紙の二冊の小さな本を見つけた。そこには思い出とともに彼が作った131書体があり、彼の生命が躍動していた。活字を本格的に追究しようと決めたのはこのときであった。 考えてみると6歳から28歳までを東洋の精神構造の中で育ち〔陶芸・俳句・和歌・詩〕、28歳から38歳まで〔石油技師〕をヨーロッパ的精神構造の中で過ごしてきた。この両極端を歩くことに私の中の魂が矛盾を感じながらバウンダリー・ゾーンをさすらっていたわけです。だから自分が何をしていいか分からなかった。 ● 1952年40歳(GHQ印刷所に入所) 私が社会人としての立場を不動のものとせず、ふらふらするのは、結局それに規定されるのがいやで、完全な自分の選択によってのみ、好きな時だけ社会人でありたいという勝手にねざしている。そして自分の中に閉じこもり、紙の上に作りものを作る。 ● 1953年41歳 いつの日に僕が僕の道を、迷いながらもためらいながらも一途に進んでいたのだ、という勝利を感じるのでしょうか。 ● 1954年42歳 『英字デザイン』丸善、1954年 ● 1955年43歳 谷川俊太郎の第3詩集『愛について』の表紙を北魏の楷書を参考にしてデザイン──その詩人〔谷川俊太郎〕の父上のことばをきいた。「なまじ書いた文字よりも、活字の方がよい」。(……)活字も、そのもとは、ヒトの書いたものであろう。書いて彫ったものであろう。そこにはどのような伝承があるのか。それをもっと完璧にするには、どうしたらよいのか。私の一生をそれにかけてもよいのではないか。 ──いつの日にか、私の手から、磨きあげた「結晶体」のような書体を生みだすことができるなら。 ● 1959年47歳 『日本字デザイン』丸善、1959年 ● 1963–66年51–54歳 『英字システム』ダヴィッド社、1963年 『ひらがな・上』文字のデザイン2、丸善、1964年 『ひらがな・下』文字のデザイン3、丸善、1965年 『カタカナ』文字のデザイン4、丸善、1966年 ● 1971年59歳 文字は国民全部の最大の文化財であって、これを扱う者はよろしく襟を正して、その公共性たることの責任を負わねばならぬ。一国の文化の将来を開く先導者として、国民に対しての義務を果たさねばならぬ。 ● 1972–74年60–62歳 『日本のタイポグラフィ:活字・写植の技術と理論』紀伊国屋書店、1972年 『漢字・上』文字のデザイン5、丸善、1973年 最初で最後の写植書体「RM-1000」の開発に着手 『漢字・下』文字のデザイン6、丸善、1976年 ● 1976年64歳 細部のすみずみまでピッタリときまった瞬間その字は、パッと花咲いたように意外な美しさに輝やく、別物のように──。そのとき「できた」と分かる。──このよろこびこそ生甲斐。 何も見ないで書いてゆき、リタッチでいろいろ試み、彫刻のようにけずり出したり、ほんの些細なところで破綻が起ったり、収まったりする。 そうして自分の判定によって、次々にその字のその字らしい調和の美が一歩一歩発見されてゆく、ときめき。「自分の中に、そうした美の規範があった!」というよろこび。 しかも それらは助手たちとの協同作業で成就する。彼らの一人一人と、やはりその急所をわかって書いた「共通の世界がわかりあえた」というよろこび。 ● 1976年64歳 活字の表情をたとえるならば「うまい水」とか「うまい空気」とでも言うほかはあるまい。 ● 1979年67歳 9月15日午前零時58分、その頭脳は考えることをやめ、その口はあふれるような活字書体への情熱を語ることをやめ、その手は文字を書くことをやめた。死因はマラリアによる心不全であった。 ──小宮山博史「佐藤敬之輔年譜 私に於て」(書体デザイナー/『佐藤敬之輔記念誌』 1982より)
佐藤敬之輔 Keinosuke Sato (1912–1969) 小宮山博史 Hiroshi Komiyama (b. 1943)
私が〔写真植字の〕研究に着手した当時は大体〈築地活版と秀英舎〉の二社が、ほとんど大きな活字メーカーであり私は、活字書体というものに全然経験がなかったので写植の文字盤を作るにあたって、そんなに面倒なものだとは思わなかった。写植の文字盤を作るにあたって始めから何種類も作るわけにはいかない。一種類の物をもって大きいものも小さいものも兼用に作らなくてはいけない。先ず中庸なものを最初に作るべきだと考えて〈12ポイント〉を基準にすることにしました。 ──石井茂吉(書体デザイナー/『季刊プリント』1号、1962より)
石井茂吉 Mokichi Ishii (1887–1963)
「これは何をお手本にして書いているのですか?」とよく聞かれるんですよ。それもまた私にとっては非常にショックだったわけですね。実は、お手本なんかはなかったんです。──小塚昌彦(書体デザイナー/『タイポグラフィ・タイプフェイスの現在』2007より)
小塚昌彦 Masahiko Kozuka
〔学生〕当時〔毎日新聞社の〕デザイン部部長だった小塚昌彦さんが活字を作っている現場を案内してくれて、帰りぎわに「文字は日本人にとって水であり米である」と言ったんです。それを聞いてえらいショックを受けて、自分はこれをやりたいと思ったのです。 ──鳥海修(書体デザイナー/『タイポグラフィ・タイプフェイスの現在』2007より)
鳥海修 Osamu Torinoumi
書体を作るのは難しいでしょうって言われるけど、俺の場合は単純で、揃って見えることと均等な空きになってればいいんだよ。 ──鈴木勉(書体デザイナー/『鈴木勉の本』1999より)
鈴木勉 Ben Suzuki
初めて「つ」を彫ったとき丸みがまずいといわれました。明朝を二、三年やってかなをやったんです。「つ」をだいぶ彫って、これでいいなと思って持っていっても、落第しちゃうんです。竹口さん〔築地活版製造所の種字彫師〕はただ駄目だというだけで、教えてくれないんです。この字はこう書けと教えないんです。持っていったものをポイッと放り投げやがるんです。とにかくひらがなを及第するのにはかなり時間がかかったんです。 ──安藤末松(種字彫り師/『日本語活字ものがたり』小宮山博史、2009より)
安藤末松 Suematsu Ando
日本の明朝体は130年ほどの伝統の上に立っています。伝統の継承とは、言葉を換えれば定型の習得ということだと思います。〔中略〕一本の線をどこに置くのか、その線に対して他の線はどう置かれるのか。書体設計上、絶対位置はありません。その線が置かれるべき範囲は、初心者では広く、経験者では狭い。この許容範囲を極限まで狭めていく作業が修行ということになります。 ──小宮山博史(書体デザイナー/『タイポグラフィ・タイプフェイスのいま。』2005より)
小宮山博史 Hiroshi Komiyama (b. 1948)
私は新しいカンバスの上にブラッシで絵を描くように、原稿紙の上に単純で鮮明なイメヂをもった文字を選んで、たとえばパウル・クレエの絵のような簡潔さをもった詩をかいていった。 ──北園克衛(詩人/『黄いろい楕円』1953より)
北園克衛 Katsue Kitasono
ひとつずつの活字を拾うことで行になり、行が集まってページとなる。ページが累積して書物ができる。 ──鈴木一誌(ブックデザイナー/『ページと力』2002より)
鈴木一誌 Hitoshi Suzuki
僕達は欧羅巴に於けるこの運動の中に、学ぶ可き多くのものを見ることが出来る。けれども彼等の活版術は、とつて以て直ちに僕達のものとすることは出来ない。殊に国語の相違から生ずる文字──活字の問題は、彼等の理論の具体的適用に於て決定的な差異点を設けてゐる。僕達は僕達の新活版術を持たなければならない。 ──原弘(グラフィックデザイナー/『新活版術研究』1931より)
原弘 Hiromu Hara
私は1950年代、デザインに手を染めた頃から、活字書体の模写に興味をもち、それぞれの書体を特徴づけるクセや偏りに注目してきた。〔中略〕漢字の一点一画が語りだすもの、仮名文字たちのつぶやきに耳を傾けながら、私は、整然たるアルファベット・タイポグラフィとは位相を異にする、活力に満ちた、「騒然たる日本語タイポグラフィ」を探求する道を歩みはじめた。 ──杉浦康平(グラフィックデザイナー/『20世紀のポスター:タイポグラフィ』2011より)
杉浦康平 Kohei Sugiura
日本語の漢字かな交じり文の視覚的なテクスチャを、欧米の均一でフラットなものに似せようとすると、どうしても文字を極端に小さくして組み、均一な濃度に仕上げようと試みることになります。そうすると当然読みにくい文字組になってしまうのが現状だと思うのです。 ──森啓(グラフィックデザイナー/『デザイン原論』2008より)
森啓 Kei Mori
タイポグラフィの目的は伝達にある。伝達は短く簡潔で、印象的な形態で行わなければならない。 ──ヤン・チヒョルト(タイポグラファー/「要素的タイポグラフィ」1925)
ヤン・チヒョルト Jan Tschichold
これからの書物は未来派の考えに合った、未来派らしい表現をもつべきである。それだけではない。私の革命は各ページのいわゆるタイポグラフィカルな調和を旨としている。〔中略〕われわれは同じページに3色も4色もインクを使うだろう。必要なら20種以上の異なる書体を使うかもしれない。このようなタイポグラフィカルな革命と多彩な色使いによって言葉の表現力は倍加する。 ──F. T. マリネッティ(詩人/「自由態の言葉」1913より)
F. T. マリネッティ Filippo Tommaso Marinetti
優秀なタイポグラファーは文字間の距離に敏感だ。文字は黒、文字間は白。タイポグラフィとは白い部分のことだ。重要なのは文字間の空間なんだ。音楽を作るのが音符ではなく、音符と音符の間なのと同じだ。 ──マッシモ・ヴィネリ(グラフィックデザイナー/映画『ヘルベチカ』2007より)
マッシモ・ヴィネリ Massimo Vignelli
私はポスターを制作する時には、常にひとつの単語をとりあげる。そして、その単語のイメージをベースにタイポグラフィを展開するんだ。 ──ウィム・クロウエル(グラフィックデザイナー/『見果てぬ未来のデザイン』2012より)
ウィム・クロウエル Wim Crowel
僕はいつも退屈していたんだ。書体の見本を眺めながらちまちま決めるのにね。作品ごとに書体を選ぶのはおもしろい作業じゃなかった。そこで、レコードやCDのジャケットで、自分たちの書体を使うことにしたんだ。 ──ステファン・サグマイスター(グラフィックデザイナー/映画『ヘルベチカ』2007より)
ステファン・サグマイスター Stefan Sagmeister
書体は透明なグラスとして、ただ情報を入れて整理して示せばいいという考え方がある。だけど、それほど単純じゃないと思う。人は読んでいる時に書体を意識しなくても、影響は受けている。演劇や映画の配役が不適当だったら、話の筋は追えても得られる感動は薄くなるだろう。タイポグラフィも同じだと思う。書体を選ぶデザイナーは劇の配役担当と同じだ。 ──トビアス・フレール゠ジョーンズ(書体デザイナー/映画『ヘルベチカ』2007より)
トビアス・フレール゠ジョーンズ Tobias Frere-Jones
読めると伝わるは違う。読めても伝わるとは限らない。伝わったとしても意図通りとは限らない。反対に最初は読むこと自体が難しいものもある。〔中略〕とても重要なメッセージが退屈で特徴のない書体で書かれるとメッセージが伝わらない。そういう状況は多いんだ。 ──デイヴィッド・カーソン(グラフィックデザイナー/映画『ヘルベチカ』2007より)
デイヴィッド・カーソン David Carson
たとえば「木」を意味する漢字を見ると、その文字のかたちに目がいく。そして、この形がある種の決まった大きさと形をした木を思い描く手助けをしてくれる。同様に、「森」という漢字を見ると、この漢字の形状が、ある種定まった規模の森を思い描かせる。絵としての漢字に反応しているのだ。 ──ピーター・メンデルサンド(ブックデザイナー/『本を読むときに何が起きているのか』2015より)
ピーター・メンデルサンド Peter Mendelsund
私はほとんどいつもベルトルト活字鋳造所のアクツィデンツ・グロテスクを用いた。この活字書体はエレガントであると同時に通常のサンセリフ体よりも力強く、客観的性格を持っている。この書体のa, c, e, g, r, sのストロークの末端は数学的にカットされている。後に登場したサンセリフ体のように、ストロークに対して鋭角や鈍角にカットするのではなく、あくまで直角にカットしているのである。 ──ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン(グラフィックデザイナー/『私の人生』1994より)
ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン Josef Müller-Brockmann
書体設計は、もっとも保守的な読者層にあわせて変化する。優れた書体設計家は、書体に与える新しさをごくわずかな範囲に留めることが、よい結果を招くことを知っているものである。もし、読者が書体の新しさに気付かなかったり、ほとんど不満の声があがらなかったならば、それはよい書体である。 ──スタンリー・モリスン(タイポグラファー/『タイポグラフィの第一原則』1930より)
スタンリー・モリスン Stanley Morison (1889–1967)
タイポグラフィのルールを打ち破る唯一の方法は、それ自体を知ることだった。 ──ウォルフガング・ワインガルト(グラフィックデザイナー/『マイ・ウェイ・トゥ・タイポグラフィ』2000より)
ウォルフガング・ワインガルト Wolfgang Weingart (1941–2021)
インターネットが登場したことで、私たちはアルファベットの時代に戻ったのです。映像の世紀がやってきたような気がした時期もあったかもしれませんが、いまや私たちはコンピューターによって、「グーテンベルクの銀河系」すなわち書物の宇宙に連れ戻され、誰もが読むことを強いられる時代になりました。 ──ウンベルト・エーコ(哲学者/『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』2009より)
ウンベルト・エーコ Umberto Eco (1931–2016)
デザインは伝えるべきコンテンツのためにある。伝えるべき価値のないコンテンツの見栄えをよくしようと努力することは、デザイナーにとってまったく不幸なことだ。 ──ラルス・ミューラー(ブックデザイナー/多摩美術大学特別講義2015より)
ラルス・ミューラー Lars Muller (b. 1955)
おそらく私たちの作品は、昔から「良いタイポグラフィ」とされてきたものには当てはまらない。のみならず、「良いフォルム」とは何かという問いへの回答として作られてもいない。今日、意味とフォルムは、手軽でてっとりばやい消費を支えるために、世俗的で陳腐なものへと矮小化されている。私たちはこうした状況に抵抗し、作品を(触覚および視覚をもとに)体験してもらうための時間的拘束として「読解」というコンセプトを盛り込むことを常に目指している。「読解」するには、作品に意識的に関わることが必要になる。〔中略〕事実上すべてが可能になり、可能になったことすべてがまかり通るとき、新しく実験的なものは意味を失う。そして無意味な実験のみが意味を持つようになる。これはパラドックスである。 ──CYAN(グラフィックデザイナー/『アイデア』292号2002より)
CYAN CYAN
私はその時初めて‘w-a-t-e-r’が自分の片手の上を流れているふしぎな冷たいものの名であることを知りました。この生きた言葉が私の魂をめざめさせ、それに光と希望と喜びとを与え、私の魂を解放することになったのです。 ──ヘレン・ケラー(教育者/『私の生涯』1929より)
ヘレン・ケラー Helen Keller (1880–1968)
時が経ち、私たちは年を重ねます。ここYouTubeでは時間が止まります。それがインターネットの魔法です。私たちはどんな曲でも、まるで成功の絶頂期にあるかのように視聴します。ここでは音楽は古くなったり、時代に遅れになることはありません。クラシックはクラシック、ポップソングはポップソングです。 ──シェールの名曲「ビリーブ」に寄せられたあるインターネットユーザーのコメント(YouTube, 2020より)
Anonymous Anonymous
生殖、出産、成長、成熟、老年、死、さらには想起や予見などは、生きものが示す最も直観的で、反論理的で、従ってまさに最も始源に近い現象様式である。生命の消滅と生命の存続とはいわば生死を賭して同盟を誓っており、回帰(Wiederkunft)とはこの同盟の永遠の象徴なのである。この回帰が終りを始めに結びつけ、始めを終りに結びつける。生成の無窮の転変の中で、永遠の回帰を示しつつ普遍の始源が、存在の静止が現出する。〔略〕ゲシュタルト・クライスとは、いかなる生命現象の中にも現れている生の円環(レーベンスクライス)の叙述であり、存在(ザイン)を求めてつぶやかれた片言である。 ──ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー『ゲシュタルト・クライス:知覚と運動の人間学』木村敏、濱中淑彦〔訳〕、みすず書房、1975年2月28日、p. 301(Viktor von Weizsäker, Der Gestaltkreis, 1950)。
ヴィクトール・フォン・ヴァイツゼッカー Viktor von Weizsäker 木村敏 Bin Kimura 濱中淑彦 Toshihiko Hamanaka
比喩とはいったい何でしょうか、それはさまざまなイメージや名前を関連づける際に観念が見せる一種のつま先回転(ピルエット)なのです。そして、わたしたちが使う文飾、脚韻や倒置や対句といった手段とはいったい何でしょうか、それは精神的な舞踊を行う特権的な場となるわたしたち固有の宇宙をわたしたちにもまた作ろうとして、わたしたちを実利的な世界から切り離す言語のあらゆる可能性の使用にほかならないのです。 ──ポール・ヴァレリー「舞踊の哲学」松田浩則〔訳〕『ヴァレリー・セレクション』下、東宏治、松田浩則〔編訳〕、平凡社ライブラリー、平凡社、2005年4月6日、pp. 123–147。Paul Valéry, ‘Philosophie de la danse,’ 1936.
ポール・ヴァレリー Paul Valéry (1871–1945) 松田浩則 Hironori Matsuda 東宏治 Koji Azuma
(p. 12)キュービスムは沈思黙考の結果生まれたものではなかったため、それが巻き起こしたセンセーションにはなんらわざとらしさはなかった。人びとはキュービスムの作品を手に入れようとはしなかったし、名誉や宣伝に奉仕した芸術家にあやつられるような大衆への呼びかけによってそれを完成させようともしなかった。 (p. 165)デ・ステイル運動は、1917年、同名の小雑誌を中心に評論家、画家であるテオ・ファン・ドゥースブルフによってオランダで開始された。そして1931年、彼の死によって終止符を打たれた。それは形式ばらない小規模の運動であり、一人がやめると誰かが加入した。最初の数年が最も独創的で実りある時期であっただろう。メンバーには画家のモンドリアンやJ. J. P. アウトなどがいた。デ・ステイル運動が実際に行われていた時期には、関係した芸術家も雑誌も無名であった。 (pp. 165–6)雑誌『様式(デ・ステイル)』は、二次元及び二次元デザインの問題すべてに応用できる近代的スタイルの構築を意図して名付けられた。彼らの論文や実作は、人間の総合的都市環境の未来へ向けての定義であり試作品であり青写真であった。このグループは芸術分野における洗練された個人主義に対抗するとともに、異なる分野(絵、デザイン、都市計画など)の序列的な区分に異議を唱えた。 (p. 166)個人は全体の中で一度自己を失いその後に再発見されねばならない。芸術とは人間が全環境をいかに管理し秩序づけるか、その方法を見つけるために先立つモデルである。彼らの視点は社会的で因習打破的であり、美学的にも革命的であった。 デ・ステイル様式の基本要素としては、直線、直角、十字、点、長方形の面、交換可能な造形的空間(みかけの自然空間とはまったく異なる)、赤と青と黄の三原色、白い地色と黒い線などが挙げられる。このような純抽象的要素を用いて、デ・ステイルの芸術家たちは本質的な調和を構築し、表そうとした。 この調和の性質についてはメンバーによって見解が異なった。モンドリアンにとってそれは擬神秘主義的、普遍的絶対であった。リートフェルトや建築家であり土木技師であるファン・イーステレンにとっては個々の作品において達成すべき形式的調和であり、そこに刻み込まれた社会的意味づけであった。 (pp. 173–4)ここではっきりさせておこう。私は何もデ・ステイルのプログラムがより直接的に政治的であるべきだったと言おうとしているのではない。実際、左翼の政治的プログラムはこれとまったく同様の矛盾に悩むことになる。純客観性の必要をドグマ的に強調することによる主観の後退はスターリン主義の本質である。同様に、デ・ステイルのアーティストたちが人間的に不真面目であったことを示唆しようとしているのでもない。私は彼らも望んだであろうように、歴史の重要な要素として彼らを捉えたいのだ。それはデ・ステイルの目的への共感なくしてできることではない。では現在から見て、デ・ステイルに欠けていたのは何だったのか。 (p. 174)それは、歴史的要素としての主観的な経験の重要性への認識である。彼らは主観性に溺れると同時にそれを拒絶した。同様に、彼らの社会的、政治的過ちは経済決定論を信望したことにある。それは今まさに終焉を迎えようとしている時代全体に一貫した誤りであった。 アーティストはしかし、政治家よりは自分自身をあからさまに表現する。そしてしばしば彼ら自身のことをよく認識している。それが彼らの証言が歴史的に価値が高い理由である。 以下に示したファン・ドゥースブルフの宣言書には、主観性に溺れながらもそれを拒絶する歪みが痛烈に表れている。 「白! それは我々の時代の精神の色であり、我々の行動を導く明快な姿勢を示す。それは灰色でもなくアイボリー・ホワイトでもなく、純白である。白! 新しい時代の色であり、時代の出来事すべてを表明する色である。それは純粋で確実な、完全主義者の我々を表明している。白、それだけでいい。我々の背後には衰退やアカデミズムの『茶』があり、分割主義(ディヴィジョニズム)の『青』、青空の数杯、緑のほおひげの神や亡霊の崇拝がある。白、純白よ」 (p. 175)この宣言書は今、リートフェルトの椅子と似たような、ほとんど無意識の疑問を私たちに抱かせないだろうか。その椅子は椅子としてではなく、信念のオブジェとして私たちの脳裡に焼きついてしまうのである。(1968年) こうした熱っぽさは、アヴァンギャルド芸術全体に共通している。あらゆるアヴァンギャルド芸術の端緒となったと言えるキュビスムの事例として、バウハウス叢書におさめられたアルベール・グレーズのキュビスムに関する言説を参照してみればそのことがよく分かるだろう(アルベール・グレーズ『キュービスム』貞包博幸〔訳〕、バウハウス叢書13、中央公論美術出版、1993(平成5)年1月30日。Albert Gleizes, Kubismus, Bauhausbücher, 1928. [00387])。 ──ジョン・バージャー「信念のオブジェ」『見るということ』飯沢耕太郎〔監修〕、笠原美智子〔訳〕、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2005年8月10日(初出:白水社1993年4月20日)、pp. 165–175。John Berger, About Looking, Pantheon Books, 1980.
ジョン・バージャー John Berger 飯沢耕太郎 Kotaro Iizawa 笠原美智子 Michiko Kasahara
「インターナショナル・スタイル」は、この語句を最初に流布させた1932年の本において、閉じた体系として提示されてはいなかった。また、近代建築の過去・現在・未来をすべて包含するものとして意図されてもいなかった。この語句はいまや、25年前のデザインの常套文句を字義通り想像力もなく適用することを非難するのに便利となっているのかもしれない。もしそれが本当に事実とすれば、この用語は忘れさられた方がよい。1932年においては依然として勢力をふるっていた「伝統建築」は、いまや死んだも同然である。20世紀の生きている建築を、単に「近代」と呼んでよいであろう。 ── ヘンリー゠ラッセル・ヒッチコック「20年後のインターナショナル・スタイル」『インターナショナル・スタイル』ヘンリー゠ラッセル・ヒッチコック、フィリップ・ジョンソン〔著〕、武澤秀一〔訳〕、SD選書139、鹿島出版会、1978年6月30日、p. 221。Henry-Russel Hitchcock, Philip Johnson, The international style, New York: W. W. Norton & Co., 1969. pp. 193–221
ヘンリー゠ラッセル・ヒッチコック Henry-Russel Hitchcock (1903–1987) フィリップ・ジョンソン Philip Johnson (1908–2005) 武澤秀一 Shuichi Takezawa
安部: ぼくはね、実はね、テーマを考えながら書くんじゃないんですよ。みんなそう思うらしくてね。テーマはテーマはって言うんだけれど、テーマというのは後でね、この、作中人物とぼくがね、共同で考え出す……んだよテーマっていうのは。だから作中人物がテーマを思いつくまでね、ぼくは待たなきゃいけないわけね。 視点を変えるとね、わかりきったものが迷路に変わるだけですよ。たとえばぼく昔なんかに書いたことあるんだけどね。あの、犬ね、犬っていうのはほら目線が低いでしょ、すごくにおいが利くでしょ。だから、匂いでもって匂いの濃淡で記憶や何か全部形成しているわけでしょ。だから犬のね、感覚で地図を仮に作ったら、これすごく変な地図になるでしょ。体験レベルでもってちょっと視点を変えればね。われわれがどこに置かれているかという認識がぱっと変わっちゃいますよね。その認識を変える事でね、もっと深くこの状況をさ、見るということ。 安部: だからぼくはね 結局文学作品というのは。ひとつのもの。生きているものというか世界。極端に言えば世界ですね、小さいなりに生きている世界 というものを作って提供する。そういう作業だと思っていますけどね。だからお説教や論ずるということは小説においてあまり必要ないと思いますね。いわゆる人生の教訓を書くなんてことは論文やエッセイに任せればいいことで、小説というのはそれ以前の、意味にまだ到達しないある実態を提供すると。そこで読者はそれを体験するというもんじゃないかと思う。 インタビュアー: それを割合わたしなんか意味を読んでしまうと、やはり迷路に入るということ…… 安部: いや、迷路でいいんです。迷路というふうに自分が体験すれば迷路なんです。それでいいんです。終局的に意味に到達するのは 間違いですね。これは日本の国語教育の欠陥だと思う。ぼくのもなぜか教科書に出てるんですよ。見ていったら 「大意を述べよ」と書いてある。あれ、ぼくだって答えられませんね。そんな、ひと言で大意が述べられるくらいなら書かないですよ。そんな一言でね、大意が述べられるくらいだったら書かないですよ。あの、それこそ最初からぼくは大意書いちゃいます。「人生というものは、ね、赤い色をしていて、中にちょっと緑が入っている」と、例えばそれが大意だとしますね。そうしたら、そういう風に書いちゃいますよ、最初から。 よくねぇ、まぁあるよ、あの、ほら、あの、温泉なんかの地図、地図さ、案内図っていうんですか。こう、山書いてさ、道路書いてさ、こうロバがいて、花が咲いて、ね。あるじゃない、ああいうもんだよね。いや、もともとの小説がそういうもんならね、そりゃいいでしょ、あの、解説で。だけどね、あの、実際の、例えば地図っていうものはね。そんな簡単に見て、ちょっと見てもね、分かりませんけどね、見れば見るほど際限なく読みつくせるでしょ。一番いいのはまぁ航空写真とかそういうものでしょうね。無限の情報が含まれている。その無限の情報が含まれていないとぼくは作品といえないと思いますよ。まぁ、無限の情報ですよ、人間なんて考えてみたら。そういう風に人間を見るということね。見なきゃいけないし、見えるんだよということを作者は書かなきゃいけない、読者に伝えなきゃいけないですよ。 ──NHKアーカイブス NHK映像ファイル あの人に会いたい File No.088 安部公房 (あべ こうぼう)1924–93 作家 「砂の女」や「壁」など数々の前衛的な作品で世界的人気を誇る。満州育ちで、終戦で故郷を喪失したことが安部文学独特のモチーフとなっている。満州で体験したことや“小説とは何か”を語る安部公房の奥深い言葉から、安部文学とは何かが見える。1985年放送の「訪問インタビュー」を元に構成する。初回放送日2006.04.30(1985年放送の「訪問インタビュー」を元に構成)
安部公房 Kobo Abe (1924–1993)
想像のつながりが生まれるもうひとつの源泉は、本の一形態としての新聞とその市場との関係にある。グーテンベルク聖書の出版から15世紀末までの40余年間に、ヨーロッパでは2000万冊以上の本が出版された。1500年から1600年にかけては、製造された本の部数は1億5000万冊から2億冊に達した。「ごく初期から……印刷工房は、中世の修道院の作業場よりもむしろ、近代の工場を髣髴とさせた。1455年、フストとシェーファーが〔マインツで〕営んでいた印刷所では、規格化された生産ができるよう工夫されており、それから20年たつと、ヨーロッパ中のあちこちに大規模な印刷所が稼働をはじめていた」。ある特別な意味では、本は、最初の近代的大量生産工業商品であった。どういう意味でか。それには、本を、初期の他の工業製品、繊維製品とかレンガとか砂糖などと比べてみればよい。これらの商品は(ポンド、荷、反など)数量で計られる。1ポンドの砂糖はたんなる分量であり、つごうのよい荷であって、それ自身としては客体たりえない。しかし、本は、この点で我々の耐久消費財を予示するのであるが、正確に大規模複製される別個の自己充足的な客体である。1ポンドの砂糖は次の1ポンドへと切れ目なく流れていくが、本は、一冊毎に、隠者のように自足している。(とすれば、パリのような都市で、16世紀までにすでに、蔵書、つまり大量生産商品の個人的収集が、なじみの風景となっていたのも驚くにはあたらない。)〔中略〕このような観点からすれば、新聞は本の「極端な一形態」、途方もない規模で販売されるが、その人気たるやきわめてはかない本にすぎないともいえよう。一日だけのベストセラーとでも言おうか。新聞が印刷の翌日には古紙になってしまうこと──この初期の大量生産商品は、その意味で、奇妙なほどに、時間のたつにつれ陳腐化していくという近代的消費財の属性を予示するものであったが──まさにその故に、それは、異常なマス・セレモニー、虚構としての新聞を人々がほとんどまったく同時に消費(「想像」)するという儀式を創り出した。我々は、ある特定の朝刊や夕刊が、圧倒的に、あの日ではなくこの日の、何時から何時までのあいだに、消費されるだろうことを知っている。(それは砂糖と対照的である。砂糖の消費は時計によらない連続的な流れとして親交する。砂糖は悪くなることはあっても、時代遅れになることはない。)このマス・セレモニーの意義──ヘーゲルは、近代人には新聞が朝の礼拝の代わりになったと言っている──は逆説的である。それはひそかに沈黙のうちに頭蓋骨の中で行われる。しかし、この沈黙の聖餐式(コミュニオン)に参加する人びとは、それぞれ、彼の行っているセレモニーが、数千(あるいは数百万)の人びと、その存在については揺るぎない自信をもっていても、それでは一体それがどんな人々であるかについてはまったく知らない、そういう人々によって、同時に模写されていることをよく知っている。そしてさらに、このセレモニーは、毎日あるいは半日毎に、歴年を通して、ひっきりなしに繰り返される。世俗的な歴史時計で計られる想像の共同体を、これ以上に髣髴とさせる象徴として他になにがあろう。と同時に、新聞の読者は、彼の新聞と寸分違わぬ複製が、地下鉄や、床屋や、隣近所で消費されるのを見て、想像世界が日常生活に目に見えるかたちで根ざしていることを絶えず保証される。『ノリ・メ・タンヘレ』におけると同様、虚構は静かに、また絶えず、現実に滲み出し、近代国民の品質証明、匿名の共同体へのあのすばらしい革新を創り出しているのである。 ──ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』pp. 61–62
ベネディクト・アンダーソン Benedict Anderson
p. 56 ピカソほどいわゆる構図というものに無頓着な画家は他に例を見ない。彼は本質的に形態の変貌を追究する画家であり、自由奔放な夢の世界の創造者であって、四角に限られた枠の中にひとつの確固たる秩序を創り出すことはまったく不得手のようである。彼の溢れるような想像力は、ひとつの限られた世界の中に安住するにはあまりに冒険を好みすぎるのかもしれない。 いずれにせよ彼は作品を作る際、まったく構図を無視するか、さもなければ他人の作品の構図をそのまま平気で利用する。多くの「剽窃」作品が生まれてくる所以である。 pp. 67–9 一九〇〇年秋、パリに登る直前に描いた自画像の周囲に「ホ・エル・レイ、ホ・エル・レイ……(我は王なり)」と書き込んだ十九歳のピカソの自信と期待はついに裏切られなかった。この時代以後、すなわち一九〇五–六年頃より彼はぐっとセザンヌに惹かれ、やがて新しく発見された古代イベリア彫刻とアフリカ黒人彫刻への興味がそれに加わり、これらすべての流れがひとつになって、あの記念碑的な大作「アヴィニョンの娘たち」の中に注ぎ込まれる。それとともに近代絵画史の新しいページが開かれ、それまでフランスの画家たちに多く学んでいたピカソが、フランスの、否、全欧州の芸術を一変させてしまう新しい芸術運動の先頭に立つことになるのである。 ──高階秀爾『ピカソ:剽窃の論理』
高階秀爾 Hideya Takashina
How happy is the little Stone That rambles in the Road alone, And doesn't care about Careers And Exigencies never fears ‒ Whose Coat of elemental Brown A passing Universe put on, And independent as the Sun Associates or glows alone, Fulfilling absolute Decree In casual simplicity ‒ 石ころって いいな 道ばたに ひとり ころころと、 うまく歩もうなど 思わずに 危ないことも 怖がらず── その飾らない茶色の衣は 過ぎゆく宇宙がくれたもの、 おひさまのように 我が道をゆきながら 誰かと力を合わせたり ひとり磨かれ光ったり、 自らの命(めい)を果たし 尽くそうと 自由気ままな 無邪気さで── ──エミリー・ディキンソン「石ころって いいな」小谷ふみ訳(https://yori.so/letters/stone)。 Emily Dickinson, How happy is the little Stone, 1510.
エミリー・ディキンソン Emily Dickinson (1830–1886) 小谷ふみ Fumi Kotani
物の姿(イマージュ)の狩人 彼は、朝早くベッドからとびおきて出かける。頭がはっきりしていて、気持ちが清らかで、からだが夏の着物みたいにかろやかなときだけだが。べつに食べ物などは用意していかない。道々すがすがしい空気を飲みこみ、鼻を鳴らして健康なかおりを吸いこむ。猟の道具は家に置いたまま、ただ目をあけてさえいればいいのだ。目が網の代わりになって、物の姿がひとりでにひっかかってくる。 まず最初にひっかかってくるのは道の姿だ。この道は、りんぼくと桑の実をいっぱいにつけた生垣にはさまれて、その骨といってもいいような、すべっこい小石の群れや、破れた血管みたいなわだちの跡を露出させている。 それから河の姿をつかまえる。河は曲り角のところではいつも白くあわだち、柳の葉に愛撫されて眠っている。さかなが腹を返すと、まるで銀貨でも投げこんだようにきらきら光り、小ぬか雨が降りだすと、すぐ鳥はだを立てる。 風に揺れうごく麦畑、見るからにうまそうなうまごやし、小川の縁飾りをつけた牧場、こうした物の姿もつぎつぎにものにする。道すがら、ひばりやごしきひわの飛んでゆく姿もつかまえる。 今度は林の中にはいる。自分にこんなデリケートな感覚があったとは思わなかった。いろんないいにおいが、たちまちからだにしみこみ、どんな鈍いざわめきも聞きもらさない。そして、まわりの木々と心を通じあおうとして、彼の神経は木の葉の葉脈と結びついてしまう。 まもなく、感動が激しくなって、落ち着かなくなる。あんまり多くのものに気がついて、心がたち騒ぎ、こわくなってくる。そこで、林から出て、村へもどってゆく木切り職人のあとを遠くからつけてゆく。 林の外では、少しのあいだ、目がつぶれるほど、入り日の姿をじっと見つめている。太陽はいま、乱雑に散らばった燦然たる雲の衣を、地平線の上にぬいで沈もうとしている。 とうとう、頭の中を物の姿でいっぱいにして家にもどると、部屋のあかりを消す。そして、寝つくまえの長いあいだ、手に入れた姿をひとつひとつ数えて楽しんでいる。 物の姿は、思い出すままに、素直によみがえってくる。ひとつひとつがほかの姿を呼びさまし、燐のように光るこうした姿の群れは、ひっきりなしに新手を加えてふえてゆく。まるで、一日じゅう狩人に追いまわされてちりぢりばらばらになっていた山うずらの群れが、夕方、ようやく危険からのがれて、鳴きながら、畝溝で集合の合図をしているみたいに。 ──ルナール『博物誌』辻昶〔訳〕、岩波文庫赤553-4、岩波書店、1998年5月18日、pp. 15–17。Jules Renard, Histoires naturelles, 1896.
ジュール・ルナール Jules Renard (1864–1910)
私は、私こそこの異常な作品を最初に見た人間だと堅く信じてゐる。マラルメはそれを脱稿すると直ぐ〔引用者註:「骰子一擲」のこと。1897年、雑誌『コスモポリス』に初出〕、彼の家へ来るやうに私に言い寄越した。……ひどくくすんだ、正方形の、捩れ脚の木机の上に、彼は、彼の詩の原稿を置いた。さうして、低い、なだらかな、少しも「当て気」のない、殆ど自分自身に聴かせるやうな聲で読み始めた……」「私には、初めて吾々の空間に置かれた一つの思惟の形象を見るやうに思はれた……。ここにこそ、真に、拡りといふものが語り、想ひ、現し身の形を生んだのである」「──私は宇宙秩序に於ける一事件に立会ったのではなからうか。これは言はば、此の机上、此の刹那に、此の存在、此の勇者、これほど簡素な、これほど温和な、これほど天性高貴で魅力のある此の人物に依って、私に描き出された「言語創造」の観念的光景ではなかったらうか。」 ──ポール・ヴァレリー「骰子一擲のこと」『ヴァリエテ II』安士正夫、寺田透〔訳〕、白水社、1939年8月26日、pp. 165–172。
ポール・ヴァレリー Paul Valéry (1871–1945) 安士正夫 Masao Azuchi 寺田透 Toru Terada
およそ東西南北と満遍なく振分けた方角のあるところなんぞに、気のきいたバケモノが出るはずもない。この筋その筋と筋だくさんの文明の産物とは、佐太はうまれがちがう。そもそも佐太のおいたちはかの林檎の木の下の穴、その地の底を極として出発した。すでに極である。そこには東西南北はない。 ──石川淳『荒魂』1963年
石川淳 Jun Ishikawa
もしかして狂女のようなものに自分がなるとして、そのようなこともまたあり得ないことではない。 ──武田泰淳『海肌の匂い』1949年
武田泰淳 Taijun Takeda
見るという行為を一瞬も止めない。未来永劫それをつづけそうな眼であった。 ──武田泰淳『異形の者』1951年
武田泰淳 Taijun Takeda
もし死ななかったらどうだろう? もし命を取り止めたらどうだろう? それは無限だ! しかも、その無限の時がすっかりおれのものになるんだ! そうしたら、おれは一つ一つの瞬間を百年に延ばして、一物たりともいたずらに失わないようにする。そして、おのおのの瞬間をいちいち算盤で勘定して、どんなものだって空費しやしない。 ──ドストエフスキー『白痴』1868年
Der Panther Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille - und hört im Herzen auf zu sein. 豹(1907–08新詩集より) パリ 植物園にて 通りすぎる格子のために 疲れた豹の眼には もう何も見えない 彼には無数の格子があるようで その背後に世界はないかと思われる このうえなく小さい輪をえがいてまわる 豹のしなやかな剛い足なみの 忍びゆく歩みは そこに痺れて大きな意志が立っている 一つの中心を取り巻く力の舞踊のようだ ただ 時おり瞳の帳が音もなく あがると──そのとき影像は入って 四肢のはりつめた静けさを通り 心の中で消えてゆく ──リルケ『豹』1907–8年
ライナー・マリア・リルケ Rainer Maria Rilke
思考を健全にしうるのは労働によってのみであり、労働を幸福なものとしうるのは思考によってのみなのであって、両者を分離すればかならず罰があたる。 ──ジョン・ラスキン『ゴシックの本質』1851–53年、p. 48。
ジョン・ラスキン John Ruskin
市九郎は一心不乱に槌を振った。槌を振っていさえすれば、彼の心には何の雑念も起らなかった。人を殺した悔恨も、そこには無かった。極楽に生れようという、欣求(ごんぐ)もなかった。ただそこに、晴々した精進の心があるばかりであった。彼は出家して以来、夜ごとの寝覚めに、身を苦しめた自分の悪業の記憶が、日に薄らいでいくのを感じた。彼はますます勇猛の心を振い起して、ひたすら専念に槌を振った。 ──菊池寛『恩讐の彼方に』1919年
菊池寛 Kan Kikuchi
新しい作品は、本当に新しいと言える作品は、過去の作品の秩序にある変化をおこす。これまでの秩序は新しい作品が出てくる前にできあがっているものであって、その新しいものが加わった後もなお秩序が保たれるためには、たとえわずかでも、従来の秩序全体が変わらなくてはならない。 ──T.S.エリオット『伝統と個人の才能』1919年
T.S.エリオット Thomas Stearns Eliot
滅び去った民族、消え失せた集団、抹殺された国は数知れない。生ある者は、かならず死ぬ。(中略)時間は、空間によって支えられている。空間的なひろがりを拒否して、せまき個体の運命にとどまることは許されない。すべてのものは、変化する。おたがいに関係しあって変化する。この「諸行無常」の定理は、平家物語風の詠嘆に流してしまってはいけない。無常がなかったら、すべては停止する。 ──武田泰淳「わが思索、わが風土」朝日新聞社〔編〕『わが思索 わが風土』朝日新聞社、1972年11月10日。
武田泰淳 Taijun Takeda
ここでわれわれは、必ずしもいつも明瞭に意識されるとは限らない特有の困難に遭遇する。すなわち、理念と経験の間には一定の間隙が厳然として存在しているように見えて、われわれがそれを飛び越えようといかに全力を尽くしてもむだである。それにもかかわらず、われわれが永遠に努力してやまないのは、この深い間隙を理性・悟性・想像力・信仰・感情・妄想をもって、もしほかにできることがなければ荒唐無稽をもってしても克服することである。 ──ゲーテ『省察と忍従』1818年
ゲーテ Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
言葉は眼の邪魔になるものです。例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それは菫の花だとわかる。何だ、菫の花か、と思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。諸君は心の中でお喋りをしたのです。 ──小林秀雄「美を求める心」1957年
小林秀雄 Hideo Kobayashi
エジプトのピラミッドは、遠くで見るのと近くで見るのとでは様子が違います。遠くで見た場合は、どうしても言葉が必要になると思うのです。なぜかと言うと、ピラミッドは一体空に属しているのか地上に属しているのか、その判断が非常にむずかしいからです。見た時の実感はあるわけなんですが、その実感を表現できるものがあるとすれば言葉でしかない。実際にピラミッドを近くで見る場合には、物量とか石のもつ質感とか、そういうものが見えてくる……離れた場合は言葉で表すことになる。昔からそういうことが行われてきたと思うのですが。 ──若林奮、前田秀樹『対論 彫刻空間:物質と思考』書肆山田、2001年12月25日、p. 102(若林奮の発言)。
若林奮 Isamu Wakabayashi 前田秀樹 Hideki Maeda
度々説明したと同じ事をここに再び繰返すのを許して下さい。自然は球体、円錐体、円筒体として取扱われねばならぬ、その諸(すべ)てが透視法に従い、物体と面(プラン)の前後左右が中心の一点に集中さるべきである。広さを示す水平の併行線は一種の自然の区画で、吾々の目前に Pater omnipotene aeterne Dus.(全智全能永遠の神)が開展した素晴らしい光況(スペクタクル)と云って差支えはない。この水平線に交叉する鉛垂線は深みを加える。自然は拡がりよりも深みに於て見られるべきもので、この点から赤や黄色で、表される光の波動の中に空気を感ぜしめるために青の量を十分入れる必要がある。 ──エミル・ベルナール『回想のセザンヌ』有島生馬〔訳〕、岩波書店、1953年6月15日、pp. 57–8(セザンヌから著者ベルナールに宛てた手紙より。1904年4月15日付)。Emile Bernard, Souvenir sur Paul Cézanne, Paris: Société des Trente, 1912. * 有島生馬(1882–1974)は有島武郎の実弟である(http://ja.wikipedia.org/wiki/有島生馬)。
エミル・ベルナール Emile Bernard
ちょうど氷のことが講義で話題になっていた時、「滑るというのは、水の骨のことである」とわたしは発言した。 ... 「魂」という字は鬼が云う、と書きます、つまりものを云う鬼が魂です、と発言した。講堂にどっと笑いが起こった。つまり、わたしがしゃべっていても、実際はそれは鬼を招待して、その鬼にしゃべらせているのであって、そういう訳で、わたしの魂の本音はいつも鬼のしゃべっていることです。 ... 一度ある言葉に捕えられてしまうと、その言葉に繫がっているいろいろな言葉が鎖になって、わたしの欲望を縛り上げてしまう ... 「女たちが遊んでいる。道に捨てられた文字を拾う女、蜘蛛が怖いから密封テントの中で寝る女、いつも煙草の三分の一を吸っては火を消してしまう女、郵便配達の手伝いをしている女、何をしても指が痛い女、詩を書く時にいつも梨を齧っている女」この歌を聞いて、わたしたち三人は深刻に黙り込んでしまった。 ... 鬼の字が入ってきたので、張り詰めていた力がゆるんで、ほぐれ、隙間から新しく流れ込んできたものがある。戸惑いの唇がくずれて、笑いに変わった。回転する車輪のように亀鏡が笑い、その笑い声の中にわたしは虎を見た。 ──多和田葉子『飛魂』1998年5月6日。 * 本書の登場人物の名前は、右に示す通り独特である:梨水、亀鏡、煙花、紅石、指姫、粧娘、朝鈴……。著者によれば漢字を適当に組みあわせてつくられたという。そのため著者にすら読み方がはっきりしないものがあるという。漢字のイメージが組みあわされて生じるあらたなイメージ。漢字のイメージ形成力。
多和田葉子 Yoko Tawada
科学は抽象を意味し、抽象はつねに現実の貧困化である。科学的概念で記述されているような事物の形式は、しだいしだいにたんなる公式となる傾向を示す。これらの形式は驚くべきほど単純なものである。単純な公式は、ニュートンの引力の法則のように、我々の物的宇宙の全構造を包含し、説明するように見える。現実は、我々の科学的抽象によって近づき得るばかりでなく、それによって完全につかむことができるように思われるであろう。しかし、我々が芸術の領域に近接するやいなや、これが錯覚であることが判明する。なぜならば、事物の様相は無限であり、それらは各瞬間に変ずるからである。単純な公式にあてはめて、それらを了解しようとする試みはすべて無益であろう。太陽は日々に新しいというヘラクレイトスの言葉は、科学者の太陽にはあてはまらないとしても、芸術家の太陽にとっては真理である。科学者が対象を記述するときに、彼は、それを一組の数により、その物理的および化学的定数によって、特徴づける。芸術は異なった目的のみでなく、異なった対象を必要とする。もし、我々が二人の芸術家について、彼らが「同じ」風景を画いているというならば、我々の美的経験を極めて不完全に述べているわけである。芸術の立場からは、このように同一と思われているものは、全くの錯覚である。 ──カッシーラー『人間:シンボルを操るもの』宮城音弥〔訳〕、岩波文庫青673-5、岩波書店、1997年6月16日、pp. 306–307。Ernst Cassirer, An essay on man, New Haven: Yale University Press, 1944.
カッシーラー Ernst Cassirer
ヴォリンゲルが語ったような意味で「抽象」という言葉を使うとすると、「感情移入衝動」と「抽象衝動」の二つは対立している。感情移入衝動というのは、中枢的な行動を取る身体を中心として世界を組織づけて、一番自分の身体にとって心地よい要素だけで世界を作り直すということでしょう。それに対して抽象衝動というのは、要するに、自然が怖い、渾沌である、暗黒である──だからこれを何とか制御したい、鎮めたい、そこに秩序を持ち込みたい、そういう衝動です。 ──若林奮、前田秀樹『対論 彫刻空間:物質と思考』書肆山田、2001年12月25日、p. 117(前田秀樹の発言)。
若林奮 Isamu Wakabayashi 前田秀樹 Hideki Maeda
見ることは、不思議である。見るというごく当たり前の行為には、私たちの意識の及ばない何かが潜んでいる。たとえば印刷物──グラフィックデザインを見る時、私たちは、印刷された紙を見るだろうか。それとも、印刷された図像を通じて心象に結ばれる、それとは別のイメージを見るだろうか。それは、そのように簡単に区別できることだろうか。そもそもその内実を、実感に即して誰かと共有したり、客観的に説明できるだろうか。つまるところ不思議と形容せざるを得ないむずかしさ、不条理さ、不可能さに、見ることの本質があるのだろう。ならばそこには、広く、見ることの文学、あるいは見ることのポエジーがあるだろう。 ──2022年10月、女子美術大学Joshibi SPACE 1900で開催された林規章グラフィックデザイン展に寄せた文章からの抜粋
佐賀一郎 Ichiro Saga
本来それだけに備わっている手段と法則を基にして、自然現象の外見を模倣することなく、つまり、“抽象”することから生じたのではない芸術を、私たちは具体芸術と呼ぶ。〔中略〕具体芸術はその独自の性格からいって自立したもので、自然現象と等価値の存在なのだ。それは人間精神の表現であるべきで、人間精神のものと決められており、そして具体芸術は明確で曖昧さのないもので、人間の精神によって期待できるような完全なものであろう。 ──マックス・ビル「一つの見解」草深幸司〔訳〕、前掲書、p. 249(Max Bill, ‘Ein Standpunkt’ In Katalog der Ausstellung, “Konkrete Kunst,” Basel: 1944.)
マックス・ビル Max Bill 草深幸司 Koji Kusabuka
カンヴァス上で一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は具体的な要素であるのか? そうではない。 一人の女、一本の木、あるいは一頭の雄牛は、自然の状態では具体的であるが、絵の状態ではそれらは、抽象的で、錯覚で、曖昧で、思弁的である。それに反して、一本の線は一本の線、一色は一色、ひとつの平面はひとつの平面であり、それ以上でもそれ以下でもない。 具体絵画──精神は成熟の年に達した。それは、具体的なやり方でそれ自身を表明するために、明快な、知的な手段を必要とするのだ。 ──テオ・ファン・ドゥースブルフ「具体絵画の基礎についての註釈」草深幸司〔訳〕『構成的ポスターの研究』ポスター共同研究会・多摩美術大学〔編〕、中央美術公論社、2001年11月22日、pp. 247–248。(Theo van Doesburg, ‘Commentaires sur la base de la peinture concrete,’ “Art Concret,” Paris: 1930.)
テオ・ファン・ドゥースブルフ Theo van Doesburg 草深幸司 Koji Kusabuka
以下に引く〈色彩〉と〈運動〉に関するテスト氏(ヴァレリー)の所感は、〈形象〉と〈文字〉に対しても多少当てはまるところがあるのではないか。 色彩の考察で運動を説明しようとは、だれも思いつくまい、ところが、その逆は試みられているし、あるいはかつて試みられた。したがって、ここには不均衡がある。 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 144「ムッシュー・テストの思想若干」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.
ボール・ヴァレリー Paul Valéry (1871–1945) 清水徹 Toru Shimizu
わたしの見るものがわたしを盲目にする。わたしの聞くものがわたしを聾にする。この点ではわたしは知っている、というそのことが、わたしを無知にする。 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 95「ムッシュー・テスト航海日誌抄」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.
ボール・ヴァレリー Paul Valéry (1871–1945) 清水徹 Toru Shimizu
一本の線は木の葉の輪郭をとらえようとしているのだろうか。線はすぐに折れ曲がり、葉脈の一つを描き出すかもしれない。あるいはそれは木の葉の上をさまよいながらも、その向こうにひろがる空間を暗示するためのものであり、木の葉を渡る風の道のようなものにかわっていきさえもするだろう。 線はためらいながらはじまったばかりであり、単なる小さな線分にしか過ぎない。しかし単なる小さな線分であるにしても、すでにそれは生きはじめているのだ。線は出現の瞬間瞬間一つの身体である。それは線が裸婦のような生きるものの肌合いを伝える場合だけとはかぎらない。三角形や四角形といった幾何学的な記号である場合ですら、線は独自の肉体を持つことで現実のものとなるのだ。 線をひいていく私は、線を生きている。それは稚拙さの度合いによってきまるのではない、私が線を生きると感じるように、誰もが線を生きるだろう。もし人が線の出現を見、そして線の出現に自らの生を生きるならば。 ──宇佐美圭司「線の肖像:レオナルドの思考」『線の肖像:現代美術の地平から』小沢書店、1980年10月20日、pp. 149–150。
宇佐美圭司 Keiji Usami (1940–2012)
鎌倉のいわゆる谷の奥で、波が聞える夜もあるから、信吾は海の音かと疑ったが、やはり山の音だった。遠い風の音に似ているが、地鳴りとでもいう深い底力があった。自分の頭のなかに聞えるようでもあるので、信吾は耳鳴りかと思って、頭を振ってみた。音はやんだ。音がやんだ後で、信吾ははじめて恐怖におそわれた。死期を告知されたのではないかと寒けがした。 ──川端康成『山の音』1949年。
川端康成 Yasunari Kawabata (1899–1972)
西田哲学においては、したがって西田哲学的に解釈された日本語においては、知覚する主体もまた、究極的には存在しない。雷鳴が聞こえているとき、海が見えているとき、それを聞いたり見たりしている主体は、存在しない。雷鳴が聞こえているということ、海が見えているということが、存在するだけである。あえて「私」と言うなら、私が雷鳴を聞き、私が海を見るのではなく、雷鳴が聞こえ、海が見えていること自体が、すなわち私なのである。しかし、そこまで行けば、「聞こえている」「見えている」もよけいだろう。「聞こえている」とか「見えている」とか言ってしまうと、どうしても、聞いているのは、見ているのは、誰か?という問いが喚起されてしまうからだ。雷鳴が聞こえていることではなく、その雷鳴そのものが、海が見えていることではなく、その海そのものが、存在するだけだ。それらとは独立の知覚作用や知覚主体は存在しない。あえて「私」と言うなら、こんどは、雷鳴自体、海自体が、すなわち私なのである。 ──永井均『西田幾多郎:言語、貨幣、時計の成立の謎へ』2018年。
永井均 Hitoshi Nagai
五・六三二 主体は世界に属さない。それは世界の限界である。 ──ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』1921年。
ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889–1951)
混沌とした、幼虫めいた、あやかしの世界を描いたあとで、僕はいまや、もっと現実的でもっと首尾一貫した、美、善、真がそこに実在しているような、ある別世界の存在について語ろうと思いたちました──ただし、そのような世界と接触することができてはじめて、それについて語る権利と義務があたえられるのですが。 ──ルネ・ドーマル「初版への序」『類推の山』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年7月4日(初出:白水社、1978年)。René Daumal, Le mont analogue, Editions Gallimard, 1952.
ルネ・ドーマル René Daumal (1908–1944) 巖谷國士 Kunio Iwaya
彼は私たちをつぎつぎに訊問した。その問いのひとつひとつは──私たちは誰なのか、どうしてここへ来たのか、といったたぐいのしごく単純なものではあったが──私たちの不意をおそい、はらわたまで突きささってくるものだった。あなたは誰なのか? 私は誰なのか? 領事館員とか税関役人に答えるように答えるわけにはいかなかった。名前をいい、職業をいえというのか?──そんなものになんの意味があるだろう? それにしてもおまえは誰なのか? そしておまえは何なのか? 私たちの口にする言葉は──それ以外にいいようがなかったのだが──生気がなく、屍骸のように見苦しいか愚かしいかであった。私たちは今後、〈類推の山〉の案内人たちの前では、もはや言葉だけでは満足してはいられないだろうということを知ったのだ。 ──ルネ・ドーマル『類推の山』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年7月4日(初出:白水社、1978年)、p. 121。René Daumal, Le mont analogue, Editions Gallimard, 1952.
ルネ・ドーマル René Daumal (1908–1944) 巖谷國士 Kunio Iwaya
あけぼののもやのなかで高らかに鳴く鶏は、自分の歌が太陽を生むのだと思い込む。とざされた部屋で泣きわめく子供は、自分の叫びがドアをあけさせるのだと思い込む。 ──ルネ・ドーマル「覚書」『類推の山』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年7月4日(初出:白水社、1978年)、p. 191。René Daumal, Le mont analogue, Editions Gallimard, 1952.
ルネ・ドーマル René Daumal (1908–1944) 巖谷國士 Kunio Iwaya
Un soir, il me répondit : « — L’infini, mon cher, n’est plus grand-chose, — c’est une affaire d’écriture. L’univers n’existe que sur le papier. ある晩、彼はわたしに答えてこう言った。「──ねえきみ、無限なんて、もうたいしたものじゃない、──それは文字のうえの問題さ。宇宙とは紙のうえにしか存在しない。 「いかなる観念もそれをあらわしはしない。いかなる感覚もそれを示しはしない。それは話すことはできるが、それ以上ではない」 ──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 123「対話」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.
ボール・ヴァレリー Paul Valéry (1871–1945) 清水徹 Toru Shimizu (b. 1931)
パノフスキーがカッシーラーから借りた〈象徴(シンボル)形式〉とは、「精神的意味内容が具体的感性的記号に結びつけられ、この記号に同化されることになる」その形式のことであり、彼は遠近法をそうした〈象徴形式〉の一つとしてとらえてみせるのである。 ──木田元「訳者あとがき」『〈象徴形式〉としての遠近法』ちくま学芸文庫、木田元〔監訳〕、川戸れい子、上村清雄〔訳〕、2009年。Erwin Panofsky, Die Perspektive als “symbolische Form,” Vorträge der Bibliotek Warburg, 1924–25.
木田元 Gen Kida (1928–2014) エルヴィン・パノフスキー Erwin Panofsky(1892–1968)
「ざわわ、ざわわ」で始まる歌(『さとうきびばたけ』)があるが、わたしはあれを聞くと、耳が聞こえ始める時のようだ、と思う。音はあのように入ってくる──というより、起こってくる。あらゆる音が──くっきりしたのも、ただからだに響いてくる感じといった、音にもならぬ振動のようなものも──鋭いのもやわらかなのも、まだそれぞれを聞き分けるということの始まる以前に、ぜんぶ一緒になった「ざわわ」なのだ。 ──竹内敏晴『声が生まれる』中公新書、2007年。
竹内敏晴 Toshiharu Takeuchi (1925–2009)
──ベンワー B. マンデルブロ『フラクタル幾何学』広中平祐〔監訳〕、日経サイエンス、1985年1月10日、p. 155。Benoît B. Mandelbrot, “The Fractal Geometry of Nature,” revised edition, San Francisco: W.H. Freeman, 1977, 1983.
ベンワー B. マンデルブロ Benoît B. Mandelbrot (1924–2010)
──Benjamin Jotham Fry, “Organic Information Design,” Thesis for Master of Science in Media Arts and Sciences at the Massachusetts Institute of Technology, May 2000.
ベンジャミン・フライ Benjamin Jotham Fry (b. 1975)
──ルネ・デカルトの『方法序説』結晶のスケッチ、1637年。
ルネ・デカルト René Descartes (1596–1650)
──スチュアート・ブランドによる「文明の序列モデル」Stewart Brand, “Clock Of The Long Now,” 2000.
スチュアート・ブランド Stewart Brand (b. 1938)
ダニには受容器と実行器をそなえた体のほかに知覚標識として利用できる三つの知覚記号が与えられている。そしてダニはこの知覚標識によって、まったくきまった作用標識だけを取り出すことができるよう行動の過程をきしっかり規定されている。 ダニを取り囲む豊かな世界は崩れ去り、重要なものとしてはわずか三つの知覚標識と三つの作用標識からなる貧弱な姿に、つまりダニの環世界に変わる。だが環世界のこの貧弱さはまさに行動の確実さの前提であり、確実さは豊かさより重要なのである。 ──ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』日高敏隆、羽田節子〔訳〕、岩波文庫青943-1、岩波書店、2005年6月16日、pp. 22–24。Jakob von Uexküll, Georg Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 1934; 1970.
ユクスキュル Jakob von Uexküll クリサート Georg Kriszat 日高敏隆 Toshitaka Hidaka 羽田節子 Setsuko Haneda
──杉浦康平《イヌ地図》『遊』6号、工作舎、1973年。
杉浦康平 Kohei Sugiura
私たちは、ふつう、時計を使って時間を測る。あの、歯車と振子の組み合わさった機械が、コチコチと時を刻み出し、時は万物を平等に、非情に駆り立てていくと、私たちは考えている。 ところがそうでもないらしい。ゾウにはゾウの時間、イヌにはイヌの時間、ネコにはネコの時間、そして、ネズミにはネズミの時間と、それぞれ体のサイズに応じて、違う時間の単位があることを、生物学は教えてくれる。生物におけるこのような時間を、物理的な時間と区別して、生理的時間と呼ぶ。 …… 寿命を心臓の鼓動時間で割ってみよう。そうすると、哺乳類ではどの動物でも、一生の間に心臓は二〇億回打つという計算になる。 寿命を呼吸する時間で割れば、一生の間に約五億回、息をスーハーと繰り返すと計算できる。これも哺乳類なら、体のサイズによらず、ほぼ同じ値となる。 ──本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間:サイズの生物学』中公新書1087、中央公論新社、2011年11月30日、Kindle版、no. 128–133。
本川達雄 Tatsuo Motokawa
──ル・コルビュジエ『モデュロールI』吉阪隆正〔訳〕、S選書111、鹿島出版会、1967年11月1日、p. 65。Le Corbusier, “Le Modulor,” 1948.
ル・コルビュジエ Le Corbusier 吉阪隆正 Takamasa Yoshizaka
──ル・コルビュジエ『モデュロールII』吉阪隆正〔訳〕、SD選書112、鹿島出版会、1976年12月5日、p. 44。Le Corbusier, “Le Modulor II,” 1954.
ル・コルビュジエ Le Corbusier 吉阪隆正 Takamasa Yoshizaka
ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊藤公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、1982年11月30日、p. 241より。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.
ロバート・ヴェンチューリ Robert Venturi 伊藤公文 Kobun Ito
本書は建築批評のひとつの試みであると同時に、私の作品を間接的に説明するひとつの弁明でもある。というのも、私は実際に建築を設計しているので、建築に関する私の考えは必然的に実務に伴った副産物としての批評なのである。 ──ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊東公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、p. 25。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.
ロバート・ヴェンチューリ Robert Venturi 伊藤公文 Kobun Ito
単純性がうまく取り入れられないと、単調さが残るばかりである。はしゃぎすぎた単純化は味気ない建築を意味するのだ。より少ないことは退屈なことなのである(less is bore)。 ──ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊東公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、p. 39。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.
ロバート・ヴェンチューリ Robert Venturi 伊藤公文 Kobun Ito
グリッド・システムは、アメリカ中西部の街や郊外のプランとか、カイロやコルドバの柱の林立するモスクの内部など、どんな形のどんなスケールのものでも、即興的な使い方、変化に富んだ使われ方が可能である。 ──ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊東公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、pp. 244–256。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.
ロバート・ヴェンチューリ Robert Venturi 伊藤公文 Kobun Ito
「レジェ」(Leger, 1957)、「ヒロシマ」(Hiroshima, 1957)、「エドガー・フェルノート」(Edgar Fernhout, 1963)といったポスター群が私たちに示しているのは、「表現主義的モダニスム」とでも言うべきモダン・デザインのあり方である。クロウエルのデザインは、常に要素的で、対象を切り詰めてゆき、そのエッセンスだけを残すというものだが、それにもかかわらず、その表現は非常にバラエティ豊かで、しかも画面への多様なアプローチを受け入れる余地が、驚くほど残されている。 ──Kerry William Purcell, ‘Interview: Modern Method’, “Eye Magazine,” no. 79, Spring 2011.
ケリー・ウィリアム・パーセル Kerry William Purcell
人間は行為することによって祭祀の車輪を回転させ続けなければならない。それによってブラフマンは遍在する。 ──上村勝彦〔訳〕『バガヴァッド・ギーター』岩波文庫赤68-1、岩波書店、2017年5月18日。
バガヴァッド・ギーター Śrīmadbhagavadgītā 上村勝彦 Katsuhiko Uemura
(p. 47)シャネルにとって時間は「スタイル」であり、クレージュにとっては「モード」であって、これが二人のちがいなのである。 (pp. 53–4)こういうわけで、一方には伝統があり(その内部での刷新がある)、他方には変革がある(しかも暗黙の一貫性がある)。一方にあるのは古典主義(感じやすくても)であり、他方にあるのはモダニズム(親しみやすくても)である。二者の決闘を要請しているのは現代社会であると思わなければならない。というのも現代社会は──少なくともここ数世紀来──芸術のあらゆる分野で、きわめて多様なかたちをとりながら、こうした対決を巻き起こそうとしているからだ。今日この決闘がモードの分野で特に明瞭なかたちをとったのは、モードもまた文学や絵画や音楽と同等の芸術だからである。 (p. 54)それ以上に、シャネルとクレージュの対決はわれわれに以下のことを教えてくれる──少なくとも確認させてくれる。今日、新聞やテレビや映画さえふくめた情報普及の飛躍的発展によって、モードはたんに一部の女性が身につけるものではなく、すべての女性(そして男性)が見たり読んだりするものになっているのだということである。われらがクチュリエたちの新作はまさに映画やレコードと同じく、好感を誘ったり嫌悪感を抱かせたりするのである。人はシャネルのスーツやクレージュのショートパンツに、信念や偏見、感情、抵抗感、要するに自分史のすべての投影し、おそらく単純すぎる言葉だが、一言でいって好き嫌いといわれるものを投影しているのである。 (pp. 54–5)そしてこのことはおそらく、シャネルとクレージュの対決の一つの見かたをも示唆している(少なくとも読者がシャネルやクレージュを買うつもりがない限りは)。シャネルのスタイルとクレージュのモードは、われわれが読んだり見たりする日々の大いなる文化に移行していて、一つの選択の素材というより、読みかたのちがいとなるような対立を形成しているのだ。シャネルとクレージュというこの二つの名は、二行詩に欠かせない二つの韻のようなものであり、あるいは、二人のヒーローが対決する壮挙のようでもあって、それなくしては美しい物語がつくれないのである。同じ一つの記号──現代の記号──のこの二側面を切り離せないものとして結びつけてとらえるならば、そのときモードは、無駄な選択のわずらわしさをあたえるものではなく、真に詩的なオブジェとなり、二つが一つになって、両義性の深いスペクタクルをみせてくれることだろう。 ──ロラン・バルト「シャネル vs クレージュ」『ロラン・バルト モード論集』山田登世子〔編訳〕、筑摩学芸文庫、筑摩書房、2011年11月10日、pp. 47–55。(初出Marie Claire, 1967)
ロラン・バルト Roland Barthes 山田登世子 Toyoko Yamada
(pp. 140–141)事物と私たちとの関係はよそよそしいものではありません。おのおのの事物が私たちの身体、私たちの生命に直接語りかけ、人間的な性格(素直な、穏和な、敵意のある、反抗的な)を帯びています。そして逆に事物は、私たちが好んだり嫌ったりするふるまいの象徴として私たちのなかに住んでいます。人間は事物のなかに取りこまれており、事物も人間のなかに取りこまれているというわけです。精神分析学者の言い方にならえば、事物とはコンプレックスなのです。セザンヌが「画家は事物の「光輪」を描かなくてはならない」と述べるとき、彼の言いたかったのはこの点にほかなりません。 (pp. 342–346)なるほどテーブルについての辞書の定義──三本あるいは四本の支持物で支えられた水平の板であって、その上で食事したりものを書いたりするもの──をそのまま受け入れるなら、まるでテーブルの本質に肉薄したような感じがするかもしれません。テーブルに伴い得るその他のあらゆる付帯性──脚の形、刳り形〔つまり家具の装飾で、部材を刳って曲面にした部分です〕のスタイルなど──には興味がないというわけです。だがこれは知覚することではなく、定義することです。これに反して、テーブルを知覚するとき、わたしはテーブルがテーブルとしての機能を遂行する様態に無関心ではいられません。おのおののテーブルによって異なる天板を支える方式、〔天板に置かれた事物の〕重力に抗う、脚から天板に及ぶテーブル全体の独特な働きは、おのおののテーブルを独自なものにしています。木目、脚の形、木の色や年代、年代を示す落書きやかすり傷──こうした些細な特徴が重要でないとはかぎらないし、わたしにとってのテーブルの「意味」は、現前するテーブルの様相に具現するあらゆる「些細な特徴」から創発するのです。 ──モーリス・メルロ゠ポンティ『知覚の哲学: ラジオ講演1948年』菅野盾樹〔訳〕、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2011年7月10日。Maurice Merleau-Ponty, “Causeries 1948, textes établies et annotées par Stéphanie Ménasé,” Paris: Éditions du Seuil, 2002.
モーリス・メルロ゠ポンティ Maurice Merleau-Ponty
ここでわれわれは、必ずしもいつも明瞭に意識されるとは限らない特有の困難に遭遇する。すなわち、理念と経験の間には一定の間隙が厳然として存在しているように見えて、われわれがそれを飛び越えようといかに全力を尽くしてもむだである。それにもかかわらず、われわれが永遠に努力してやまないのは、この深い間隙を理性・悟性・想像力・信仰・感情・妄想をもって、もしほかにできることがなければ荒唐無稽をもってしても克服することである。 ──ゲーテ「省察と忍従」『色彩論』木村直司〔訳〕、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2001年3月7日、pp. 18–20。Johann Wolfgang von Goethe, “Bedenken und Ergebung,” 1818.
ゲーテ Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 木村直司 Naoji Kimura
芸術作品の形式は作品から分離することができない。 ──スザンヌ K. ランガー〔著〕『芸術とは何か』池上保太、矢野萬里〔訳〕、岩波新書青641、岩波書店、1967年5月20日、p. 30。Susanne K. Langer, “Problems of art,” 1957.
スザンヌ K. ランガー Susanne K. Langer 池上保太 Yasuta Ikebami 矢野萬里 Mari Yano
およそ東西南北と万遍なく振分けた方角のあるところなんぞに、気のきいたバケモノが出るはずもない。この筋その筋と筋だくさんの文明の産物とは、佐太はうまれがちがう。そもそも佐太のおいたちはかの林檎の木の下の穴、その地の底を極として出発した。すでに極である。そこには東西南北はない。 ──石川淳『荒魂』1964年より
石川淳 Jun Ishikawa
二、三日前から「幽霊」という短篇を書き出した(註。この長篇は初め母が家出するまでの短篇として書きだされ、次第にふくれあがって長篇となったものである。)「マルテ」の影響が大きい。良いものができそうだ。 ──北杜夫『或る青春の日記』昭和25年[1950年]の日記より、中央公論社、1988年11月7日(初出:「中央公論文芸特集」1987年春季号~1988年夏季号)、p. 387。
北杜夫 Morio Kita
人はなぜ追憶を語るのだろうか。どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだ。その神話は次第にうすれ、やがて時間の深みのなかに姿を失うように見える。──だが、あのおぼろな昔に人の心にしのびこみ、そっと爪跡を残していった事柄を、人は知らず知らず、くる年もくる年も反芻しつづけているものらしい。そうした所作は死ぬまでいつまでも続いてゆくことだろう。それにしても、人はそんな反芻をまったく無意識につづけながら、なぜかふっと目ざめることがある。わけもなく桑の葉に穴をあけている蚕が、自分の咀嚼するかすかな音に気づいて、不安げに首をもたげてみるようなものだ。そんなとき、蚕はどんな気持ちがするのだろうか。 ──北杜夫『幽霊』冒頭、1956年自費出版、 1960年中央公論社から刊行。
北杜夫 Morio Kita
そこにそうしていると、波の音と、水の激動が、僕の感覚を定着させ、僕の魂から一切の激動を駆逐して、魂をあるこころよい夢想の中にひたしてしまう。そして、そのまま、夜の来たのを知らずにいることがよくある。この水の満干、水の持続した、だが間をおいて膨張する音が、僕の目と耳を撓まず打っては、僕の裡にあって、夢想が消してゆく内的活動の埋め合わせをしてくれる。 …… 僕は長い一生の有為転変の中にあって気づいたのだが、最も甘美な享楽と、最も強烈な快楽の時代というものは、その追憶が僕を最も惹きつけ、感動させる、そういった時代では案外ないものである。あの夢中と熱狂の短い時期は、それがどんなに激しかろうとも、また、その激しさそのもののために、実は、人生という線の中のまばらな点々にすぎないのである。それらの時期が、一つの状態を構成するには、あまりに稀有であり、あまりに早く過ぎ去る。そして、僕の心が思慕する幸福というのは、消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態なのである。それ自身においては、激しい何物も有していないが、その持続が魅力を増加していって、ついには、そこに最高の幸福が見いだされるにいたる、そういう状態なのである。 ──ルソー「第5の散歩」『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂〔訳〕、新潮文庫、新潮社、2016年3月25日。Jean Jacques Rousseau, “Les Reveries du Promeneur Solitaire,” 1782.
ルソー Jean Jacques Rousseau 青柳瑞穂 Mizuho Aoyagi
真に重大な哲学上の問題は一つしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。 ──アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』清水徹〔訳〕新潮文庫、新潮社。Albert Camus, “Mythe de sityphe,” 1942.
アルベール・カミュ Albert Camus 清水徹 Toru Shimizu
ぼくの眼は千の黒点に裂けてしまえ 古代の彫刻家よ 魂の完全浮游の熱望する、この声の根源を保証せよ ぼくの宇宙は命令形で武装した この内面から湧きあがる声よ…… ──吉増剛造「疾走詩篇」冒頭『黄金詩集』1970年より
吉増剛造 Gozo Yoshimasu
茶店にすわれるは 疲れたる旅びと。 そは余人ならず 道楽むすこ。 ──ヘルマン・ヘッセ『クヌルプ』高橋健二〔訳〕、新潮文庫、新潮社、2016年4月22日。Hermann Hesse, “Knulp,” 1915.
ヘルマン・ヘッセ Hermann Hesse 高橋健二 Kenji Takahashi
数日来ほとんどたえずそうだったが、今また彼は心の中で神さまの前に立ち、ひっきりなしに神さまと話していた。彼は恐れは少しもいだかなかった。神さまはわれわれにたいし何もしないことを、彼は知っていた。ふたりは、神さまとクヌルプは、互いに話しあった。彼の生涯の無意味だったことについて。 …… 「いいかい」と神さまは言った。「わたしが必要としたのは、あるがままのおまえにほかならないのだ。わたしの名においておまえはさすらった。そして定住している人々のもとに、少しばかり自由へのせつないあこがれを繰り返し持ちこまねばならなかった。わたしの名においておまえは愚かなまねをし、ひとに笑われた。だが、わたし自身がおまえの中で笑われ、愛されたのだ。おまえはほんとにわたしの子ども、わたしの兄弟、わたしの一片なのだ。 ──ヘルマン・ヘッセ『クヌルプ』高橋健二〔訳〕、新潮文庫、新潮社、2016年4月22日。Hermann Hesse, “Knulp,” 1915.
ヘルマン・ヘッセ Hermann Hesse 高橋健二 Kenji Takahashi
思考を健全にしうるのは労働によってのみであり、労働を幸福なものとしうるのは思考によってのみなのであって、両者を分離すればかならず罰があたる。〔…〕画家は自分で使う顔料を擦りつぶすべきであり、建築家は石工の現場で部下たちとともに働くべきだ。工場主は工場の誰よりも腕の立つ職工であるべきだ。そして人と人を区別するのは経験と技量の差だけであるべきで、権威と冨巳はそれに応じて自然かつ正当に獲得されるべきものなのである。 ──ジョン・ラスキン『ゴシックの本質』川端康雄〔訳〕、みすず書房、2011年10月7日、pp. 48–49。John Ruskin, ‘The Nature of the Gochic,’ “The Stone of Venice,” 3 vols., London: George Allen, 1851, 53.
ジョン・ラスキン John Ruskin
市九郎は一心不乱に槌を振った。槌を振っていさえすれば、彼の心には何の雑念も起らなかった。人を殺した悔恨も、そこには無かった。極楽に生れようという、欣求ごんぐもなかった。ただそこに、晴々した精進の心があるばかりであった。彼は出家して以来、夜ごとの寝覚めに、身を苦しめた自分の悪業の記憶が、日に薄らいでいくのを感じた。彼はますます勇猛の心を振い起して、ひたすら専念に槌を振った。 ──菊地寛『恩讐の彼方に』1919年。
菊地寛 Kan Kikuchi
狂女はとりかえしのつかぬ異端者になっている。それはどうしようもない。淋しくおそろしいことではあるが、もうきまってしまったことだ。自分は彼女とはちがう。しかしもしかしたら……、と市子は思った。もしかして狂女のようなものに自分がなるとして、そのようなこともまたあり得ないことではない、と彼女は思った。 ──武田泰淳「海肌の匂い」『展望』1949年10月号。
武田泰淳 Taijun Takeda
滅び去った民族、消え失せた集団、抹殺された国は数知れない。生ある者は、かならず死ぬ。(中略)時間は、空間によって支えられている。空間的なひろがりを拒否して、せまき個体の運命にとどまることは許されない。すべてのものは、変化する。おたがいに関係しあって変化する。この「諸行無常」の定理は、平家物語風の詠嘆に流してしまってはいけない。無常がなかったら、すべては停止する。 ──武田泰淳「わが思索、わが風土」朝日新聞社〔編〕『わが思索 わが風土』朝日新聞社、1972年11月10日。
武田泰淳 Taijun Takeda
男の胸は鋼のひかりもて鎧ふべし血のなかの鹽いたきかな ──塚本邦雄『感幻樂』1969年。
塚本邦雄 Kunio Tsukamoto
君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く ──額田王(万葉集より)。
額田王 Nukatano Okimi
私が1913年に芸術を対象的なもののバラストから解き放とうと死にものぐるいの努力で、正方形のかたちに活路を求め、白い地に黒い正方形しか描かれていない作品を発表したとき、批評家も、彼と一緒になって世間も嘆息まじりにこういったものだ「私達が愛情を注いできたものすべてが失われてしまった。私達は砂漠にいる……眼前にあるのは白い地の上の黒い正方形だけだ!」と。 ──カジミール・マレーヴィチ『無対象の世界』五十殿利治〔訳〕、バウハウス叢書11、中央公論美術出版、1992(平成4)年4月25日、p. 66より。Kasimir Malewitch, “Die Gegenstandslose Welt,” Bauhausbücher, 1927.
カジミール・マレーヴィチ Kasimir Malewitch
「〔……〕芸術の使命は自然を模写することではない、自然を表現することだ。君はいやしい筆耕ではない、詩人なんだ」と老人は頭ごなしポルピュスをさえぎって、強く叫んだ。「さもなければ彫刻家は、女をそのまま鋳型にとれば、ほかになんにも仕事はいらんわけじゃないか。ところでね、ためしに君の愛人の手を鋳型にとって、目のまえにおいてみたまえ。まるで似もつかない恐ろしい死骸に出くわすだけだろう。そうして君は、彫刻家ののみを求めにいかずにはいられなくなるだろう。彫刻家はその手を正確に写しとることはしないが、その動きと生命を君に彫り上げてみせるだろう。われわれは事物の精神を、魂を、特徴をつかまえなくてはならない。 ──オノレ・ド・バルザック「知られざる傑作」『知られざる傑作 他五篇』水野亮〔訳〕、岩波文庫赤529-1、岩波書店、1928年11月25日、p. 150。Honoré de Balzac, “Le Chef-d’œuvre inconnu,” 1831.
オノレ・ド・バルザック Honoré de Balzac
人物を描くひとは、もしかれが対象になりきることができないなら、これをつくりえないであろう。[Ash. I. 33 v.] 運動は一切の生命の源である。[Tr. 36 v.] ──レオナルド・ダ・ヴィンチ『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』上、杉浦明平〔訳〕、岩波文庫青550-1、岩波書店、1954年12月5日、p. 237。
レオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci
すべての間違いの元は、唯一無二の「本当の自分」という神話である。 そこで、こう考えてみよう。たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて「本当の自分」である。 ... 一人の人間は、複数の分人のネットワークであり、そこには「本当の自分」という中心はない。 個人を整数の1とするなら、分人は、分数だとひとまずはイメージしてもらいたい。 私という人間は、対人関係ごとのいくつかの分人によって構成されている。そして、その人らしさ(個性)というものは、その複数の分人の構成比率によって決定される。 分人の構成比率が変われば、当然、個性も変わる。個性とは、決して唯一不変のものではない。そして、他者の存在なしには、決して生じないものである。 ──平野啓一郎『私とは何か:「個人」から「分人」へ』講談社、2012年9月20日。
平野啓一郎 Keiichiro Hirano
〔テレパシー能力を脳組織切除手術によって封印し、所属していたテレパシー部隊を除隊したエレノアは、この物語の主人公ベントリーを誘惑する〕「あたしは部隊にとどまっていたかったんだと思うの。でもあたしは部隊が憎かった。ひとの心をのぞきこんで、耳をすまして、心に起こることをなんでも知ってしまうなんて。独立した人格として生きているとはいえないわ。一種の集団的有機体よ。愛することも憎むこともできない。あるのは仕事だけ。それも自分の仕事じゃない。そんな生活を八十人のひとたちと、ウェイクマンのようなひとたちとわかちあわなければならないのよ」 ──フィリップ・K. ディック『偶然世界』ハヤカワ文庫SF 241、早川書房、1977年5月30日、p. 123。Philip K. Dick, “Solar lottery”, 1955.
フィリップ・K. ディック Philip K. Dick
「おほかた人のまことの情といふ物は、女童(めのわらは)のごとく、みれんに、おろかなる物也、男らしく、きつとして、かしこきは、実の情にはあらず、それはうはべをつくろひ、かざりたる物也、実の心のそこを、さぐりてみれば、いかほどかしこき人も、みな女童にかはる事なし、それをはぢて、つゝむとつゝまぬとのたがひめ計也(ばかりなり)」 ──本居宣長「紫文要領」巻下。出典:小林秀雄『本居宣長』上巻、新潮社、Kindle版・No.2367–2370。
本居宣長 Norinaga Motoori
美は痙攣的なものだろう、それ以外にはないだろう。 ──アンドレ・ブルトン『ナジャ』巖谷國士、岩波文庫赤590-2、岩波書店、2003年7月16日、p. 191。Andre Breton, “Nadja,” 1928.
アンドレ・ブルトン Andre Breton 巖谷國士 Kunio Iwaya
──マックス・エルンスト『百頭女』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年3月4日。初出:河出書房新社、1974(昭和49)年。Max Ernst, “Le femme 100 têtes,” 1929.
マックス・エルンスト Max Ernst 巖谷國士 Kunio Iwaya
──陰陽図。高田眞治、 後藤基巳〔訳〕『易経』上・下巻、岩波文庫 青 201-1/2、岩波書店、1969年6月16日・同7月16日より。
陰陽図 Yin-yang diagram
直立姿勢のおかげで、空間はヒト以前の存在には無縁な構造──「上」–「下」を貫く中心軸から水平に広がる四方向──に組織された。言い換えれば、空間は人体の周囲に、前後、左右、上下にひろがるものとして組織されるのである。方向づけ(オリエンタツィオ)のさまざまな方法は、この根源的経験──無限の、未知の、驚異的なものに見えるひろがりのただなかに「投げこまれた」と感じること──から生じた。なぜなら、人間は方向づけを失うことによってもたらされる混乱状態に生きながらえることはできないからである。「中心」の周囲に位置づけられたこの空間体験は、領土、集落、住居の、範例的な分割と配置の重要性と、その宇宙論的シンボリズムの重要性を説明する。 ──ミルチア・エリアーデ『世界宗教史』第1巻、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2000年、p. 22より[Mircea Eliade, “Histoire des croyances et des idées religieuses,” 1976]。
ミルチア・エリアーデ Mircea Eliade (1907–1986)
イーフー・トゥアン『空間の経験:身体から都市へ』山本浩〔訳〕、ちくま学芸文庫ト2-1、筑摩書房、1993年11月4日、p. 69。初出:筑摩書房、1988年8月25日。Yi-Fu Tuan, “Space and place,” the University of Minesota, 1977.
イーフー・トゥアン Yi-Fu Tuan
ストーンヘンジの平面プラン。Wikipedia
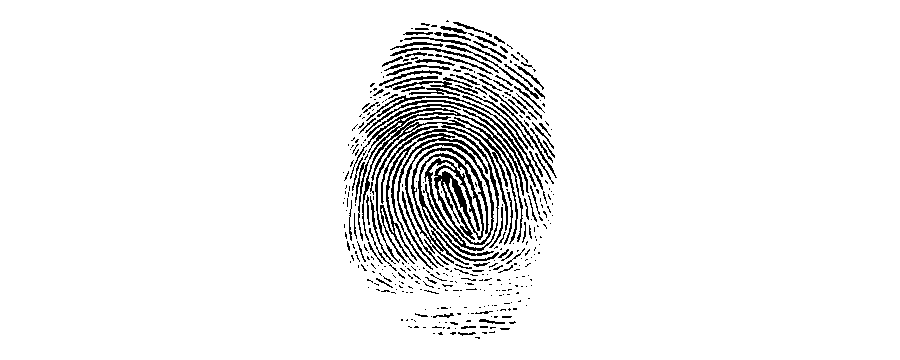
ストーンヘンジ Stonehenge
↑